最近の日本が不景気なのは否定できない事実だと思います。
個人の見解に過ぎませんが、不景気になった理由を整理したいと思います。
前提として、やはり企業、個人の消費が減ることが不景気に直結していると考えます。
①100均等、ファストフード等安い店の台頭
デフレが良くないのはよく言われますが、それの原因の1つは劇的に安いお店の台頭だと思います。
100円で物が買える・(スリーコインズなどで)300円で物が買える。80円でハンバーガーが食べられる。300円で牛丼が食べられる。
それらはありがたい一方で、個人の消費額を劇的に減らすものと思われます。
従来だったら300円で買われていたものが、100円で買われる。700円くらいランチに使われていたものが300円で済まされる。確実に消費額は下がりますよね。
家具屋で言えば、ニトリなど私もよく使いますが、仮に昔は2万円していた家具が1万円で売られていたら、消費額は減ります。
ちなみに、こういった劇的に安いお店の台頭により潰れたお店も多いように思います。
②もったいないの精神
一時期、日本のもったいないの精神がもてはやされたと思いますが、景気だけを考えた場合、もったいないの精神はかなりマイナスに働くと思います。
いわゆる、リデュース、リユース、リサイクルの話ですね。特にリデュースと、リユース。
リデュースについては、商品の替え時が5年が適正とした場合に、もったいないからといって10年みんなが使うとしましょう。それだけで、単純に消費が半分になると言えます。
リユースについては、①とも近いですが、リサイクルショップ、フリマサイトなどの台頭が影響していると思います。新製品を買ったら消費額が高いですが、リサイクル品だと、消費額がかなり抑えられます。尚、フリマサイトなどは消費税などもかかりませんし、税金も取れないことになります。
③派遣労働、外国人労働者の増加
派遣は基本的に給料が少ないです。よって派遣が増えると、当然、収入が少ない人が増えます。収入が少ない人は当然、消費額が少ないです。
外国人労働者も同様です。外国人労働者も給料が少なく、消費は少ないです。また本来、外国人労働者が入らなければ、給料を上げて人を集めるしかなかったのに、外国人労働者が入ることで、給料を上げずに雇用ができてしまうケースが多数あります。これも給料が上がらない原因となり、消費の増加のチャンスを潰すことになっています。
派遣の規制を緩くした竹中平蔵さんなどには大きな責任があると思います。
④国内に周るお金が減った
私も最近まで知らなかったのですが、実は小泉元首相、竹中平蔵さんの郵政民営化も不景気の一旦を担っています。郵政の郵貯とかんぽ、それらにはたくさんお金があり、それらは当然運用されておりました。運用はすなわち、どこかに投資するということですが、従来は主に日本に投資されていたようです。郵政民営化がされた結果、外資が郵貯やかんぽの株を買うようになり、それら外資の株主の影響で海外の投資率が増加したという話です。当然、日本に投資されていたら、そのお金を使って色々な消費がされますが、海外に投資されたら、その分のお金が国内で消費されません。その意味で、郵政民営化は日本の景気に大打撃を与えたと言えます。
また、経済格差が増えたのも大きな要因として考えられます。収入が比較的少ない人は、収入が増えれば、消費が増えます。収入が減れば、消費を減らさざるを得ません。その一方で収入が100億円の人が、120億になったからといって、消費はほとんど変わらないでしょう。
このように、お金持ちが派遣や外国人労働者により安い労働力で人を雇って私腹を肥やすと消費が冷え込むものと考えられます。
⑤法人税を減税して、個人に対して増税を行った
完全に政府の失策です。失策というか、意図的なのかもしれませんが。
法人税が高い場合、企業は利益をたくさん出しても税金をたくさん取られることになります。それだったら経費を増やして、すなわち、従業員の給料を増やしたり、投資をしたりしようという発想になる人もいると思いますが、税金が少ないのであれば、それらを控えて、蓄えを増やすことも多くなると思います。給料が増えないのは消費の増加を抑制しますし、投資をしないのは直接的に消費を減らします。実際、企業の内部留保の額はかなり増えています。*もちろんリスク対策の意味もあるとは思いますが。
個人に対しての増税は、手取りを大幅に減らします。当然使えるお金が減り、消費は減ってしまいます。さらに将来の不安から余計に消費を控えるようになってしまいました。
⑥外資企業、外国資本の参入・優遇
消費がなされても外資企業が儲かってしまうのでは、あまり意味がありません。郵政民営化でがん保険の外資、アフラックが儲かったことがあります。それ以外にもgoogleやyoutubeを始めとするデジタル的な損失があったり、P&G、コカ・コーラ、各種製薬のような外資メーカーが利益を伸ばしていたら、その分、国内メーカーへの消費が減ってしまうことになります。
また、国内メーカーが売り上げを伸ばしていた場合でも、株主の比率が外国資本が多ければ、配当金は外国に流れていくことになります。
その意味では配当金割合が低く従業員に対する還元が多い会社は日本の消費に大きく貢献しているように思われます。
また、最近は、ソーラーパネルや電気自動車の普及を進めたりしていますが、それらは中国企業が儲かるだけです。たまたま中国企業が儲かるなら仕方ない気もしますが、補助金や再エネ賦課金でそれらを優遇するのは、日本にとってマイナスしかないと思います。再エネ賦課金で実質的に国民の使えるお金が減るのも消費の低下につながります。
⑦少子化・高齢化
少子化・高齢化も当然、消費を減らします。子供が生まれると色々とお金がかかります。服もどんどん買い替えていく必要があります。旅行に行かせたり、塾や習い事などにもお金が使われます。その一方でおじいちゃんやおばあちゃんはあまりお金を使いません。服だって10年も同じものを着たりしています。医療費がかかり、それの大部分が保険料から支払われるため、増税の原因になっています。*社会保険料も実質的には税金です。海外では普通に税金の位置づけです。
増税が給料の手取りの低下をもたらし、消費を減らしてしまいます。
少子化・高齢化は仕方ない部分がありますが、お金が無くて結婚できない、だから子供も作れないという理由は大きくあると思われ、無策で増税ばかりする政府の責任も大きいものと思われます。
その他 生産性について
よく、竹中平蔵さんがテレビで批判された時に言うのが「日本は生産性が上がっていないことが問題だ」という内容なのですが、個人的には生産性という言葉に対して非常に違和感があります。
例えば、農家1人がどれだけ1年間で米を作ったか、この企業が一年間でどれだけ車を作れるか、みたいな話はそれなりに生産性の話だと思います。
しかし、そういった生産業、メーカー以外はどうでしょうか。
日本のマクドナルドの店員の質がアメリカより低いですか?日本の飲食店の質(提供スピード、味含め)がアメリカより低いですか?
全然そんなことは無いと思います。むしろ基本日本が上でしょう。
もちろん、色んな製品の質も日本は高い水準にあると思います。
それらを踏まえると、生産性は、給料次第なだけだと思います。
経営者がしっかりと高い給料を従業員に支払うことが重要で、場合によってはそれを価格に転嫁して物価が上昇するのが健全なのだと思います。
外国人を入れて給料を下げることこそ、見た目の生産性を下げているように考えられます。
米山隆一議員が先日何かのメディアで、地方の企業などは人手不足で困っているところが多いから外国人は必須だ、という旨の主張をしていましたが、個人的には、全然理由になっていないように思いました。
外国人が入って嬉しいのは、そこの経営者とそこから献金を受ける、政治家くらいですよね。
一般人はそこの会社が潰れたところで何ら問題がありません。従業員はそこが潰れたら他の会社で働けば良いですし、本当に需要がある内容なら、誰かが代わりに会社を作るはずです。外国人が入ると、それによって給料が上がらなかったり、働き口が減って仕事につけなかったり、単純に治安が悪くなったりで不利益のみを被ります。今後AIで仕事が減ったら尚更困ります。
まとめ
以上、考えられる不景気の理由を列挙してみました。
全体的には、国の政策が外国やお金持ちに寄りすぎなのが問題のように思われました。
まあ、お金持ちの大企業や中国、米国が政治家に献金をしまくっていたら(賄賂もあるでしょう)、それ寄りの政策になりますよね。
日本が良い方向に変わって欲しいものです。

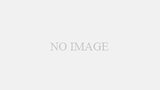
コメント